
研究開発
私たちは研究開発を積極的に行い、結果を汎用技術へ、ミドルウェア製品へ、サービスへと拡張してきました。全従業員の約7割、100人超が音と映像を専門とする技術者です。当社が大切にしている「社会の豊かさを先進技術で支える」ための研究開発活動について紹介します。
当社の研究開発
音と映像で豊かな未来を作るために

ミドルウェアは特性上、製品やサービスに組み込まれ世の中に提供されます。当社はただミドルウェアを提供するだけでなく、プロジェクトの立ち上げから運用まで、全てのフェーズに伴走できるよう研究開発をしています。
既存の課題から「こういうことはできないか?」といった相談ベースの問題にも対応するため、業界の課題や最新技術動向の把握はもちろん、当社自身が想定した社会的課題に対しても、日々、研究開発を進めています。
研究開発内容や成果
当社が得意とする音と映像、さらにそこから派生したさまざまな領域について、研究内容を紹介します。
主な研究領域
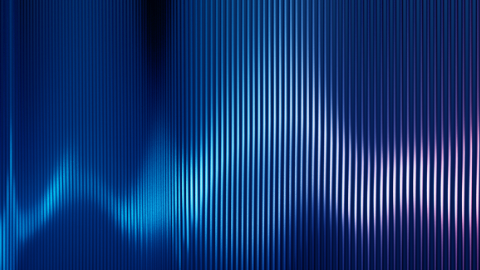
音声
音声信号処理、音声コーデック、音声分析、音程/声質変化、楽曲解析、サウンドオーサリング、圧電素子音声出力、高音質アンプ、筐体/音場補正 など

映像
映像解析、動画再生、動画圧縮、動画ストリーミング、動画の重ね合わせ、α動画(透明度付き動画)、動画エンコード制御、VR映像、映像コーデック、映像最適化 など

2D/3Dグラフィックス
圧縮、減色、リアルタイムCG、画像最適化、画像認識、超解像、アニメーション など

通信
Web API開発、先読み/遅延ロード、Webブラウザ制御 など

クラウド
複数人での同時編集、音や映像の再生と編集、WebRTC、レスポンス高速化 など

AI
機械学習、ビッグデータ解析、ゲーム機や組込み機器などへの展開 など

UI/UX、HMI
直感的な操作、簡単な操作、間違わない操作、少ない操作回数、ツールの構築 など
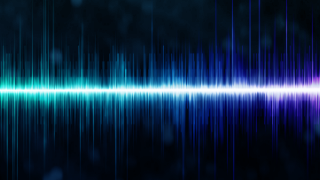
その他
振動、地図情報連携、動作実行中のデータ交換 など
研究成果の発表
当社は研究開発の成果を積極的に外部に発信しています。
ゲーム開発者向けカンファレンス「GDC 2025」にて登壇
2025年3月開催
•Thou Art Truly a Brave Audio Designer! ‘Shadowgate’,‘Dejavu’and ‘Uninvited’ Audio Design of ROM Cartridge Era
ゲーム開発者向け技術カンファレンス「CEDEC」にて登壇
2024年8月開催
・シン・和音解析 裏拍でも乗っていこう -音符長窓幅を採用した新しい和音解析-
・言語の壁を超えろ!ゲームエンジン上で「安全に」「ラクして」ネイティブライブラリを使う取り組み
・VRゲーム「 ブレイゼンブレイズ 」で、より良い音場表現を追求してみた-イマーシブオーディオ実装の知見とノウハウ-
・わたしこそ しんの サウンドのゆうしゃだ! -ROMカセット時代のサウンド制作-2023年以前も多数登壇
「情報処理学会」にて招待講演
2024年8月開催 第141回音楽情報科学研究発表会にて
・リアルタイム音声処理システムの構成
技術に関するデータ
技術関連のデータをご紹介します。
-
CEDEC 公募講演数
CEDECの公募セッション登壇には、厳しい審査を通過する必要があります。この登壇数は、当社の発表が業界全体の発展に寄与する新規性と価値があると認められた証です。
19本
-
エンジニア比
当社は音声や映像の技術に強みを持つメンバーが多数集まっている会社です。全体で7割を超えるエンジニアたちは、日々切磋琢磨しながら研究開発を行っています。

研究開発を促進するさまざまな社内制度
当社には社内の自主的な研究開発を促進する複数の制度があります。制度を通じて「失敗を恐れない」「気になったことを突き詰める」という社内風土を醸成、さまざまな領域でノウハウを蓄積しています。
-

自主研究から将来の製品化も可能な「チャレンジ奨励制度」
年に2回、自らテーマを設定し研究、成果をまとめて発表する「チャレンジ奨励制度」を設けています。現在の担当業務に直接関係していなくても社員自身が「こんな技術や製品があれば」と考えたことを発表し、表彰します。ここで発表された技術が、正式に製品化された実績も多数あります。
-

エンジニア主体のショートプレゼン「LT(ライトニングトーク)」
週に1回、エンジニアが主体で実施するLTを開催しています。5~15分という短時間でプレゼンテーションを行うもので、他のメンバーや会社、さらには社会や業界に役立つテーマを選定して発表します。内容は技術トレンドや自身が試してみたことの共有が多く、社内での知見の共有やコミュニケーション促進に役立っています。
-

技術カンファレンスへの登壇を推奨
会社全体で社員の技術カンファレンス登壇を積極的に推奨しています。「若者よ登壇せよ」をキャッチコピーに、ベテランだけでなく若手の登壇も後押し。報奨金も設定しています。
研究開発で得られた知見を会社内に留めるのでなく、積極的に発信、共有することでよりよい社会の構築を目指しています。





